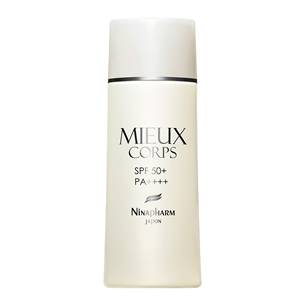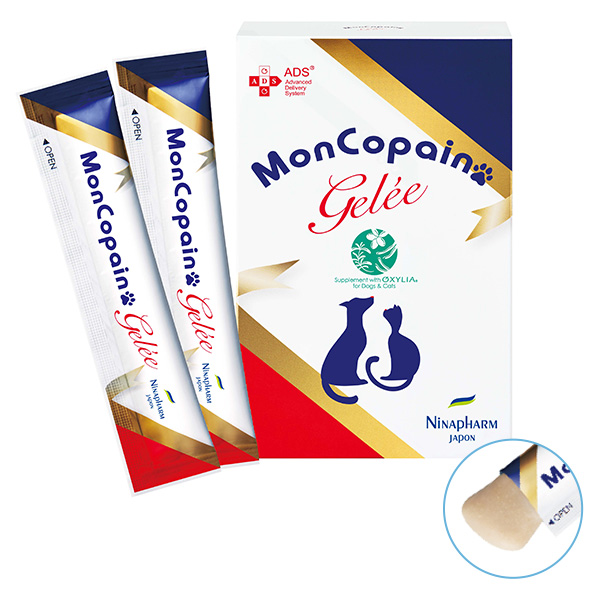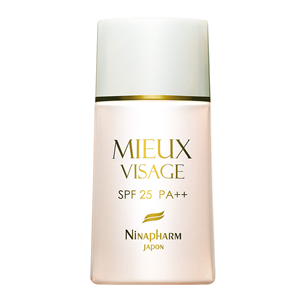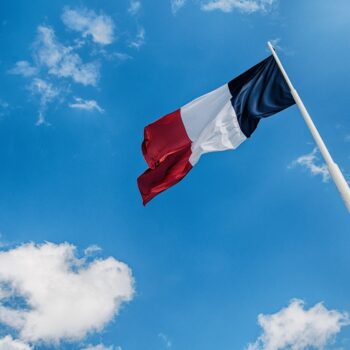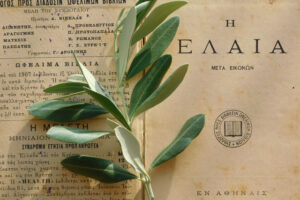摂取と消費のバランスが大事【カロリー】②

食事と運動のバランスに加え基礎代謝アップも効果的
一般的に食物のカロリーは、その料理の100グラム中に含まれる炭水化物、脂質、たんぱく質の量を分析し、アトウォーター係数と呼ばれる規定のカロリー数を掛けて合算して出しています。
炭水化物、たんぱく質は1グラムあたり4kcal、脂質は同9kcalです。炭水化物、たんぱく質に比べて脂質のカロリーは倍以上ですから、同じ分量の料理であっても脂質が多ければカロリーも高いということになります。これが、脂っこいものを食べ過ぎると太るといわれる根拠です。
食事によって体内に取り込むエネルギーを「摂取カロリー」と呼びます。これに対して、基礎代謝や運動などによって使われるエネルギーは「消費カロリー」です。
摂取カロリーが消費カロリーを上回れば、その分が中性脂肪として蓄積され、体重は増加します。一方、消費カロリーが摂取カロリーを上回れば、蓄積された中性脂肪がエネルギーに変換されるので、体重は減少します。
従って、体重を維持するためには常に摂取カロリーと消費カロリーを同じにすればいいということになります。つまり体重が増加気味になってきたら、摂取カロリーを減らす(=食事の量を減らす・質を変える)か、消費カロリーを増やせ(=運動をする)ばいいわけです。
ここで気をつけたいのが、食事によって体内に摂取しているのはカロリーだけではないということです。食物繊維やビタミンなど、カロリー以外にも体に必要な要素をたくさん摂っているので、食事を単純に減らすわけにはいきません。適度な量の食事を摂り、それに合わせて運動の量を増やすのが最も健康によいということになるわけです。
もうひとつ、消費カロリーを増やす手段として、基礎代謝を上げるという方法があります。
消費カロリーのうち、60~70%が基礎代謝ですから、こちらを上げる方が消費カロリーアップには効果的です。基礎代謝は10代でピークを迎え、あとは下降の一途を辿ります。若い頃と同じような食生活を続けていると徐々に太ってしまうのです。食べる量を減らすと同時に、筋肉を鍛えて基礎代謝を上げることも効果的です。